「その時」から相続は始まっています
肉親やご親族と充実した日々を過ごされているあなた。
でも、残念な事に不幸はいつやってくるかわかりません。
あなたは「その時」の準備をされていますか?
「まだまだ自分には関係なさそう。」
「相続の話なんて縁起でもない!」
「相続なんて、法律で決められた通りにすればいいんでしょ。」
「うちは財産なんて無いから、関係ないよ。」
そう思われている方は、是非「相続の流れと手続き」を読んでみて下さい。
相続の流れと手続き
「相続」はいつから始まるのでしょうか?
【民法 第882条】
相続は、死亡によって開始する。
いつから相続の手続きを始めようか・・・ではなく、相続は死亡によって自動的に開始されてしまいます。
相続人の考えは関係ありません。
自動的に開始される相続によって、亡くなった方の「権利義務関係」はすでに宙に浮いてしまっているのです。
相続人は、すみやかに宙に浮いた権利義務関係を確定しなければなりません。
死亡(被相続人の死亡)
死亡届の提出と埋葬許可証の取得→市町村役場
(死亡後7日以内ですが、通常はご葬儀の前に手続きします。)
銀行・郵便局等の口座凍結
(原則、関係者からの連絡で凍結されますが、金融機関の判断で凍結されることが多いです。)
ご葬儀が終わられたら
各種手続き
「権利義務関係の変更」手続きも大きな意味で相続の一部となります。
電気・ガス・水道等の契約者名義変更
新聞・インターネット等の契約者名義変更または解約
携帯電話・クレジットカード等の解約
健康保険証の返却・変更
厚生年金・国民年金の手続き
健康保険の手続き
年金受給権者死亡届
加給年金額対象者不該当届
世帯主変更届
介護保険の手続き
老人医療受給者の手続き
特定疾患医療受給者の手続き
身体障害受給者の手続き
児童手当の手続き等
葬祭費支給申請
埋葬費支給申請
死亡一時金の請求権
死亡保険金の請求権
遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求権
寡婦年金の請求権
※上記手続きは、亡くなられた方の状況により変わります。
ご葬儀も終わり、ほっと一息・・・
各種手続き(権利義務の変更)だけでも気が遠くなりそうですね。→各種手続変更代行はこちら
でも、相続はここからが本番です。
遺言書の確認
お亡くなりになられた方の「遺言書」の有無を確認します。
残されていた場合には、原則家庭裁判所で「検認」の手続きをします。
※公正証書遺言は検認の手続きが必要ありません。
相続人の確定
遺産を受け取ることができる方は「法定相続人」と呼ばれます。
しかし法定相続人以外に、遺言書に書かれている方にも受け取る権利が発生することがあります。
「遺産分割」後のトラブルを回避するためにも、相続人の調査・確定は確実に行いましょう。
残された財産の調査
遺産を受け取ることができる方を特定したら、次は受け取る財産を確定します。
相続財産はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産(負債)も含まれます。
しっかりと「財産目録」を作成しましょう。
※財産目録は一部の相続人で作成すると、他の相続人から「隠し財産」の存在を疑われる場合があります。
専門家に公平な立場で作成してもらうことが、後々のトラブル回避につながります。
相続の方法を決定する
プラスの財産とマイナスの財産が確定したら、相続の方法を決定します。
すべての相続人が、同じ方法で相続しなければなりません。
プラスの財産もマイナスの財産も、すべて相続します。
プラスの財産額を限度として、マイナスの財産も相続します。
財産の相続をすべて放棄します。
※相続放棄は相続人の一人からできます。
3ヶ月を過ぎると、たとえ負債がプラスの財産を上回っていても、単純承認になってしまいます。
遺産分割協議書の作成
「誰が」、「何を」、「どれだけ」受け取るかを協議し、決定した内容を書面にし記名押印します。
「財産の価値認識」は人によって様々です。
遺産分割協議は、相続の中で最も難しい(揉める)手続きなので、専門家にまかせることが安心です。
分割された遺産の名義変更手続き
銀行・郵便局等の口座の解約・名義変更
土地・家屋等の不動産の名義変更
車・バイクの名義変更
株式・証券・国債等の売却・名義変更
相続税の申告・納付
必要な申告をしなかったり、申告の期限を過ぎてしまうと、追徴課税が発生してしまいます。
相続の終了
相続はそのうち・・・などと考えていると、あっという間に10ヶ月は過ぎてしまいます。
ギリギリであわてないためにも、相続は専門家に依頼しましょう。
いかがですか。
相続は法律で大枠は決められていますが、遺産分割は一つとして同じ事例はありません。
時間の浪費や後々の親族間のトラブル・・・そんな後悔をしないためにも専門家にまかせてみませんか?
「相続」を真剣に考えてみましょう
相続対策に「まだ早すぎる」はありません。
「そのとき」をイメージして考えてみてはいかがでしょうか。
もし、疑問や不安があったら、一度「相続の専門書士」にご相談ください。
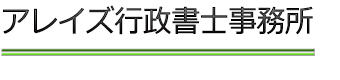

![cdc[1]](http://arays-gyousei.com/wp-content/uploads/2013/09/cdc11.gif)
